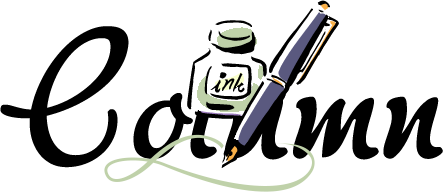牛乳を広口の鍋に入れ、静かに加熱すると表面に膜が張ることは皆さんもよくご存じのことと思います。全く同様に豆乳から作られるものが「湯葉」です。「湯葉」とはなかなかしゃれた名前ですが、牛乳の膜にはこのようなすてきな名前は付いていません。っていうか、むしろ1000年以上日本人は無視し続けてきたのではないかと思われます。そこで、今回は乳皮についてスポットを当ててみることにしましょう。
何年も前のことですが、日光の湯葉屋さんに見学に行ったことがあります。天井が高く、天井に近い位置に窓があります。この窓の位置が重要で、豆乳の表面から盛んに水分が蒸発する仕組みになっています。皮膜生成には蒸発がポイントになります。科学的には「ラムスデン現象」と呼ばれ、熱と蒸発により液面にて局所的な変性(液体と気体の間に起きる界面変性)と濃縮が起き、たんぱく質と脂肪を主成分とする皮膜が生成します。液面をよく見ていると、しばらく加熱していると表面に小さなシワができます。このシワがやがて集まり、液面全体に広がり膜を作ります。これをすくい上げ、物干しのような針金につるします。そうこうしているうちに2枚目の膜ができます。3枚目、4枚目と次々に膜をすくい上げ、鍋が焦げ付く前に終了します。膜の成分は、最初はたんぱく質と脂肪が多く、終わりに近づくと糖質の割合が増えてきます。当然味も変化し、早い段階ですくい上げた湯葉は生湯葉に、終わりの方の湯葉は油でかりっと揚げ、塩をまぶすとビールのつまみにピッタリです。
牛乳の皮膜に関する研究は世界的にも殆ど行われていません。論文数も限られています。恐らく、欧米には湯葉チックな乳製品がないためでしょう。しかし、グローバルには皮膜を利用する乳文化があります。平田先生の「人とミルクの1万年」によれば、インドの「ラブリー」やモンゴルの「ウルム」が乳の皮膜利用製品です。私は食べたことはありませんが、大変美味だそうです。
ラブリーとウルムでは作り方はビミョーに違うようですが、加熱中に牛乳をすくい上げて落とすという操作を繰り返す点が湯葉の作り方とは大きく異なります。「すくい上げて落とす」という操作は牛乳を泡立てる、すなわち含気工程です。含気すれば、空気と接する面積が飛躍的に大きくなり、気液界面変性を効率的に起こすことができます。
では、「ウルム」に似た美味なる乳皮利用製品は日本には伝わらなかったのでしょうか。中国にてAD530年~AD550年頃編纂された「斎民要術」は7世紀には日本に伝わったと考えられています。この本の中に乳加工に関する記述があり、乳皮の作り方も書いてあります(図参照)。

生乳を弱火で加熱しながら何回もすくい落とし、皮膜を作ります。この製法はモンゴルの「ウルム」と同じです。皮膜をすくい採った残りを発酵させたものが「酪」であり、皮膜は「穌」を作る時に使用すると述べています。
一方、皆様もご存じの「涅槃経(ねはんきょう)」では、「生乳から酪を作り、酪から生穌を作り、生穌から熟穌をつくり、熟穌から醍醐を作る」と書いてあります。皮膜は登場していません。このため、皮膜はできるものの無視されてしまったか、全量を穌の製造に使い、中間製品である皮膜を口にしなかったのかもしれません。貢穌の命により穌の製造に携わった人々は、朝廷に献上するモノなので、味見をすることを禁じられていたのかも。あるいは、口の狭い容器に乳を入れて加熱した場合、液面からの蒸発が不十分だと膜はできにくくなります。
ちょっとしたことに気付くか気付かないかが技術の分かれ目になる一つの例かと思います。子牛を近づければ搾乳できることに気付いた人々は乳利用を可能にしました。一方、気づかなければ何年動物と暮らしていても乳利用技術を手にすることはできません。同様に、皮膜を味見しておいしいことに気付いた人々は密かに食べ、やがて日本に乳文化が定着したかもしれません。まさしくコロンブスの卵なのですね。