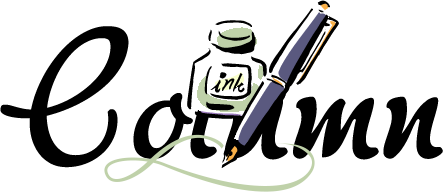今回はバターの話ですが、まずこの大量に山積みされたラディッシュの写真を見てください。こうした光景はフランスの市場へ行けば普通に見られます。日本ではこのラディッシュは、せいぜいサラダの彩りに使われるくらいで一般の消費量は極めて少ないのでしょう。スーパーの野菜売り場で見かけることはまれですね。ではフランスではこの大量のラディッシュをどうやって食べるかといえば、なんとバターと一緒にオードブルなどで食べるのです。パリで子育てをした人が書いた本にも子供の小学校の給食にもラディッシュのバター添えが出たとありました。フランス料理ブームなどといわれてから数十年、何でも取り入れる日本人なのに、なぜこうしたシンプルなものが広がらないのか不思議です。

日本でバターが本格的に造られたのは、今から130年くらい前だったようですが、一般の食卓に登場するのはもっと後の事です。バターといえば、日本ではトーストしたパンに薄く延ばすというやり方が普通でした。従ってバターが冷たくて固いと塗りにくくて不便。そこで初期の頃の冷蔵庫には温度が高いバター専用のケースが付いていたのです。しかし、これはバターの品質を落とすという事でやがてなくなります。そうこうしているうちに、1968年に大手企業がソフトマーガリンを発売するに及んで、バターはマーガリンに取って代わられるのです。かつて日本のバター消費の大部分はパンに塗る、でしたから塩味が付いた有塩バターが大半でした。ちなみにフランスでは、無塩で発酵させたバターが主流なのです。1960年代に大手が発酵させた「ファーメント・バター」なるものを発売しましたが、成功しませんでした。現在の売り場にはわずかながら発酵バターが見られます。

かつてフランス料理では、バターは料理の決め手になる基本的な食材でした。フランスの食事情に詳しい作家の宇田川悟氏は「良質のバターさえあれば、たとえどんな場所にいようと美味しいフランス料理ができる」「おいしい料理はバターから生まれる。他のもので代用できない大切な材料だ」と、フランスを代表するグラン・シェフに言わせています。かれらが最も評価したのがノルマンディー産のバターでした。しかし、1970年代に隆盛を極めたヌーヴェル・キュイジーヌは料理の簡素化、濃厚なソースの廃止、軽さの追及などを基本的な理念とし、これによって一時バターは重要視されなくなっていきます。しかし1980年代になると混乱をきたしたヌーヴェル・キュイジーヌに代わって、伝統的な技法を尊重しながら、時代に合った技法を融合させるという古典料理への回帰が現れるようになるとバターを使ったソースも徐々に復活してきたようです。

さて、日本にはランス料理に使えるバターはあるのか。最近各地で優れた手づくりのバターが造られているようですが、東京に高級フランス料理店を開いたMOF(フランス国家最高職人賞)のジョエル・ロブションは、日本のバターはあまり良い物ではないといっている。巨匠はバターの品質に厳しいのです。ちなみにロブション氏は、かつてグラン・シェフの御用達だったノルマンディーのイジニィ産のバターを抜いて人気上昇中のボルドーの北部のシャラント地方のバターを評価しています。20世紀の前半、現代フランス料理の巨匠を多く輩出した南仏のレストランのシェフ、フェルナンポワンの口癖は「さあ、もっとバターだ!」だったといいます。