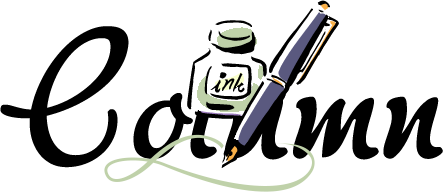先月と同じく、まだ北イタリアの美食街道をたどっている。このあたりは、「チーズときどき食文化」でも紹介した通り、圧倒的な生産量を誇るパルマの生ハムで世界に知られているが、その陰でひっそりと作られてきた生ハムがある。それがクラテッロ(Culatello)である。私がこの名を知ったのは1997年に出版された「イタリア 味の原点を求めて」(白水社)であった。この本はパスタやチーズや白トリュフなどいくつかの素材を詳しく解説したもの。クラテッロの項では生ハムの王者と書かれていたが、当時はあまり関心をひかなかった。それから10年チーズ関係のグループとイタリアの旅に登った。ワインやペコリーノ、バルサミコ酢、パルミジャーノなどの工房を訪問のあと、最後にはなんとその、クラテッロが食べられるというのだ。思ってもいなかったチャンスである。

ポー川の畔の、クラテッロの中心地といわれるジベッロ村に向かう途上、私はイタリア在住の高名なライターが書いた前述の本の、クラテッロの項を思い返した。パルマを過ぎて間もなく高速を降りて、北に向かう田舎道を走ると間もなくポー川の南岸にあるジベッロの町が見えてきた。この町を中心にせいぜい一辺が15kmほどの四角い地域がクラテッロの聖地なのだ。このあたりはバッサ(低湿地帯)と呼び、秋から冬にかけて地元民が「壁のような」と表現する濃霧が一日中立ち込める。この霧が極上のクラテッロを育てるのだという。私が初めてパルマを訪れた時は晩秋で、50m先が見えない濃霧が大地を覆い滞在中の3日間一度も晴れなかったので、風景写真は一枚も撮れなかったほどだ。

クラテッロは元来、自家用や贈り物として作られていたという。仕込むのは12月。作り方は豚の臀部の上等の肉だけを切り取って塩をもみ込み、5~7kgほどの洋ナシ型に成形して薄い袋(昔は豚の膀胱を使った)に入れて熟成庫に1年あまり吊るして熟成させる。古典的な製法は、冬は、レンガなどでできた部屋で窓から濃霧を入れながら熟成を行い、春には土間のある貯蔵庫に移して秋まで熟成させるというのが、昔からのクラテッロの作り方の概要である。したがって冬の濃霧、夏の暑さ、バッサと呼ぶこの地域の水位の高さなどの条件がそろわないと、本物のクラテッロは出来ないと地元の人は信じている。

やがてこの生ハムは美食家の間で話題になり始めると、当然商品となるクラテッロを作る企業が現れるが、そこには保険所とEUの検査官が介入してくる。古典的な製法では何から何まで現代の食肉加工の衛生基準の合わないのだが、地元の人々は、手術室並みの衛生的な設備で作ったものはクラテッロではなく、普通の生ハムになると主張する。
さて、我々一行は小さな集落で車を降り、両側にバラが咲くエントランスを通り、レンガ造りの古い建物に入った。半地下の部屋に案内されるといきなり、目の前にびっしりとカビに覆われたクラテッロが無数にぶら下がっているのだ。壁も床もレンガ作りで、この様子ではどう見ても保険所やEU検査官のOKは出そうもない。とすれば自家用なのだろうか。クラテッロの熟成室の見学は10分程でおしまい。その後ここで熟成しているらしいパルミジャーノやサラミが試食に供されたがクラテッロは出なかった。

外に出て少し歩くと牧草地があり牛や馬が草を食んでいる。バッサと呼ぶこのあたりの土地は川の水面より低いので牧草地も土の堤防に囲まれている。今日はこの旅の最後の昼食だ。穏やかな田園風景の中を歩き木立に囲まれた「白馬亭」なる小さなレストランに入った。仲間たちはワインなどを飲みながら談笑していると、突然、鮮やかなバラ色の生ハムが現れた。クラテッロだ!仲間たちは歓声を上げ、その美しさに見とれていたが、みな満面の笑みを浮かべて口に運んだ。このクラテッロがお上のおメガネにかなった工場製なのか、はたまたヤミの自家製なのか我々には判断のしようがなかったが、みな先ほど見た熟成室の、あのクラテッロを思い描いていたに違いない。