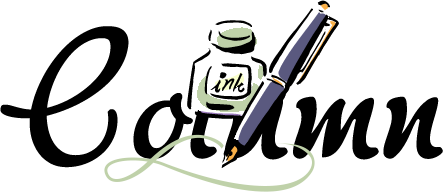関西出身の作家、開高健氏に『モンゴル大紀行』という写真集があり、その本の冒頭に同郷の司馬遼太郎氏との対談がある。その中で司馬氏は遊牧の起源について「極力家財を少なくし家畜の群れを引き連れて移動する遊牧という生活様式は、紀元前800年頃黒海の北岸に住んでいたスキタイ人によって始められた」としている。そして、その時引き連れていた家畜は山羊と羊の混成部隊であったとし、それに対し開高氏は「ヒツジはアホやから密集して一か所の草を根こそぎ食いよるので草原は砂漠化する。だから常に移動したがる山羊を入れるとその群れは一か所にとどまらないので砂漠化が防げる」。それを知らなかった古代のギリシャ人は羊の群れによって国土を荒廃させ、古代ギリシャ文明が滅んだのではないかと司馬氏はいっている。私はこれを読んでわだかまっていたモンゴル高原への旅の目的が明確になり出発を決めた。モンゴルに精通する旅行社を探し、現地では普通の遊牧民のゲルに宿泊し彼らと同じものを食べて過ごすという条件を出し旅の企画を頼んだ。
そして、6月の中旬に単身羽田からモンゴル行きに乗り込む。5時間でウランバートルだ。空港をでると私の名を書いた紙を掲げる男が達者な日本語で話しかけてきた。自己紹介が済むと、この旅の案内人はすぐに三菱の四駆に私を乗せて走り出す。まもなく公道を外れ、草原の道なき道をたどり始める。50kmほど走ったか。やっと2個のゲル(移動式テント)が見え、そこから蒙古犬が猛然と吠え掛かってくる。しかし案内人の男はこのゲルじゃないといい、さらに走り続けやっと緩やかな斜面に3つのゲルを探し当て、ここだ!と叫ぶ。吠え掛かってきた犬達も案内人とは顔馴染みの様ですぐおとなしくなる。ゲルに到着すると夫婦と3人の子共たちに紹介されるが言葉は全く分からない。しかし一家の人懐こい穏やかな笑顔に気持ちが和らいだ。ここには家族が暮らす大きなゲルが2棟と、他に少し離れたところに客用の小さなゲルが1棟ある。想像するに、草原で遊牧民と過ごしたいという物好きのために現地の旅行社が客用にこのゲルを設置し、この一家に管理させているようである。夕食が済むと乾燥牛フンが燃えているこの小さなゲルで眠りにつく。高原の星空は壮絶としか言いようのない明るさであった。6月とはいえ夜は寒い。
翌朝、早起きして日の出前にゲルを出て周辺を散策する。快晴無風であった。改めて回りを歩いてみると、樹木らしきものは一本もなくすべてが萌え始めた貧弱な草が大地を覆っている。日が昇り始めるとゲルの人達は、小動物の群れを夜間の狼よけの狭い囲いから解放する。それが終わると朝食だ。まずはこの家の少年が丼一杯のスーテーツアイ(塩味の乳茶)を運んできたが、朝食は案内人の男が町で買ってきたパンで少しがっかり。朝食が済むと少年は姉と二人で小動物の群れを決められた方向に誘導し野に放つ。彼らは一群となって草を食べながら草原を進んでいくが、それほど遠くへは行かないようだ。
朝食が終わって陽が高くなると、目の前の草原をいくつもの家畜の群れが通り過ぎていく。そこで、筆者は旅の目的の一つである家畜の群れの観察に取り掛かる。目の前の丘の中腹に寝転んで通り過ぎて行く小動物の群れを眺めた。どの群れも山羊と羊の混成部隊で先頭を切って行先を決めるのはやっぱり山羊のようである。時間が経つと昨夜の寝不足がたたって眠ってしまったが、草原での昼寝は何にも代えがたい爽快な経験であった。昼頃ゲルに戻ると、この家の主婦と娘さんが自家製のヨーグルトやバターらしきもの、そしてアーロールと呼ぶチーズ作りを見せてくれたのだが、その製法は今から800年ほど前にマルコ・ポーロが『東方見聞録』に書いた作り方とそっくり同じなのには驚かされたのであった。
■「世界のチーズぶらり旅」は毎月1日に更新しています
©写真:坂本嵩/チーズプロフェッショナル協会
*禁無断転載